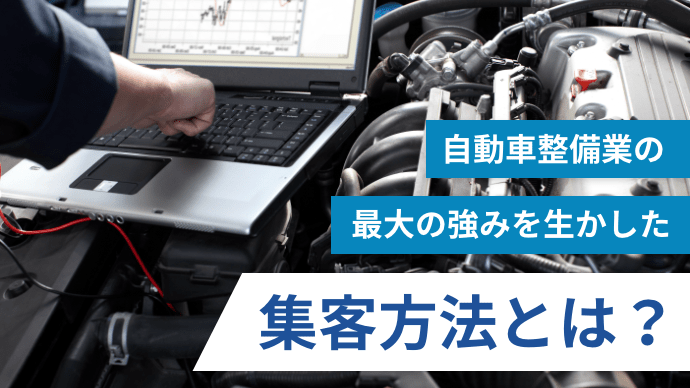業界トレンド
盛り上がる“ラストワンマイル物流“ 、一方で進む事業者の淘汰
投稿日:2023/02/20更新日:2023/02/20
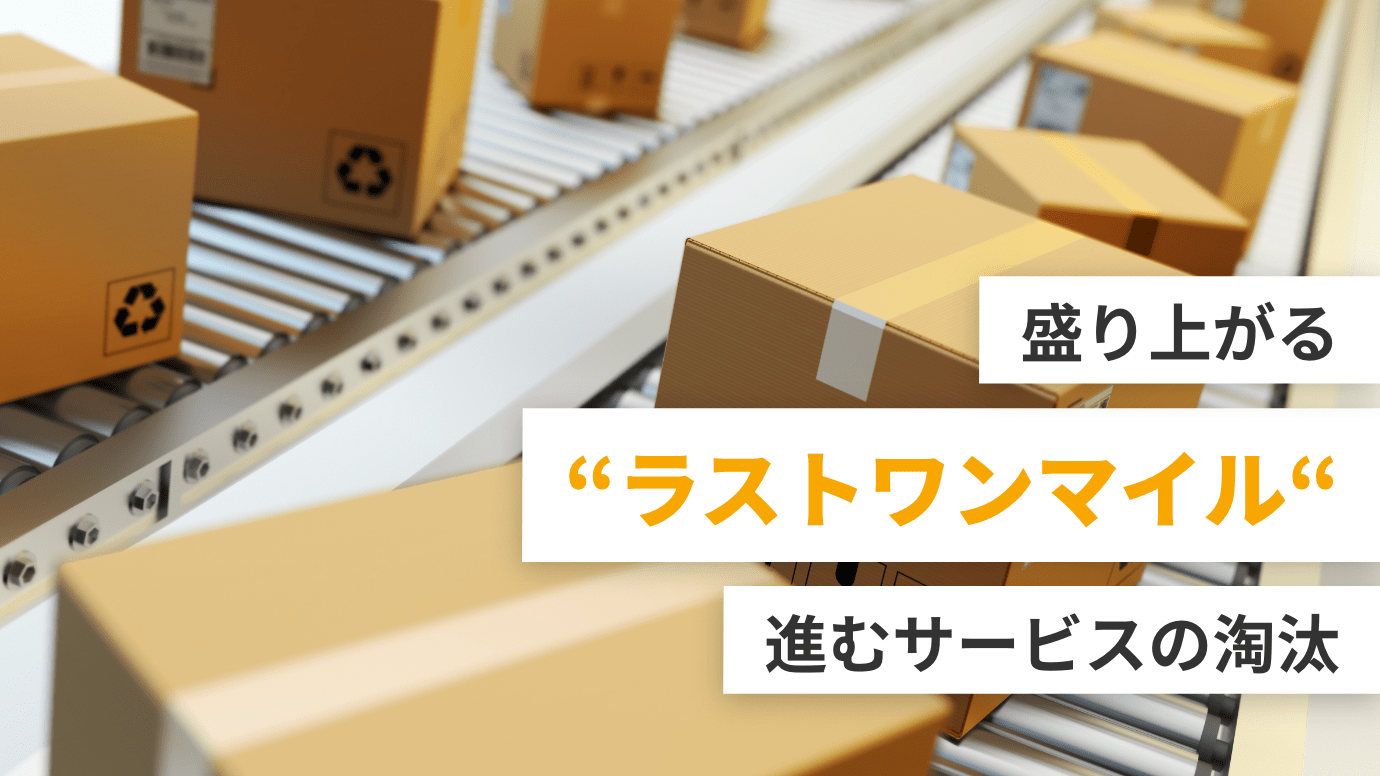
今晩の夕食を作り始めてから料理に必要な食材がないことに気づき、手元のスマートフォンを使って注文したら数十分で自宅に商品が届いた―――。近年、飲食店やコンビニの代わりに商品の配達を担う「配送代行サービス」が活況です。
こうした、最終的な集荷拠点(店舗)から生活者の自宅までの区間(ラストワンマイル)の物流は、新型コロナウイルスの流行によって人々のライフスタイルが変化する中で社会インフラとして浸透してきました。対象の配送カテゴリは料理に始まって食品や日用品、医薬品などに拡大しており、ラストワンマイル物流の市場成長が見込まれています。
EC需要増でラストワンマイルの市場が拡大

Eコマース(EC)市場の拡大に伴い、宅配便の取り扱い個数が大きく伸びています。緊急事態宣言の際の外出制限などによる「巣ごもり需要」によって、ECサービスを利用される機会や回数が増加しました。今後も、テレワークや遠隔教育が普及することで、需要のさらなる拡大が見込まれます。
調査会社の矢野経済研究所によれば、2022年度のラストワンマイル物流の市場規模は2019年度比で143%の2兆8,560億円と推計されています。市場は、全体の約6割を占めるEC販売が今後も拡大し、堅調に推移する見通しです。
生活者のEC需要の高まりを受けて多くの小売業がEC事業に力を入れる中、これを新たな商機と捉えて様々なラストマイルデリバリーのサービスや事業者が登場しています。
食品や日用品、医薬品などに取り扱いカテゴリが拡大

ラストワンマイルの配送形態として、需要が発生したタイミングで仕事を請け負うギグワーカーに頼ったデリバリーサービスが「シェアリング・エコノミー」として社会に浸透してきました。
その先進国である米国では、フードデリバリー最大手のDoorDashが2020年6月、ドラッグストアチェーンのCVS Pharmacyと提携し、店舗を拠点に日用品やOTC医薬品などの配達を開始しました。加えて、ネット専用コンビニであるDashMartを立ち上げ小売業に参入。店舗販売せずに、インターネット経由で購入された商品を配達する事業を展開しています。一方で業界2位のUber Eatsは、2021年に酒類宅配業者の米Drizlyを買収。配達する商品のラインナップ拡充を進めています。
国内の動きをみると、既に乱立のデリバリー事業者に淘汰が進んでいます。フードパンダを手がけるドイツのDelivery Heroは、2021年12月に日本からの撤退を発表しました。韓国発の同業FOODNEKOの買収で規模拡大を目論んだものの、上陸から約1年半での撤退となりました。
最後発のDoorDashは、地方からサービス展開。2021年6月に宮城県仙台市でサービスを提供開始して以来、宮城県の他のエリアや、岡山県、埼玉県、北海道とエリア拡大を図ってきました。2022年8月に日本でのサービスが終了し、ブランドをWoltに統合しています。
Woltは、中長期的には人口カバレッジを目標とした戦略に切り替え、「社会インフラ」として機能するようになることを目指しています。現在では、日本においても料理のみならず、日用品、食料品、医薬品まで配達の対象が拡大し、Woltではこれを「ポケットの中のショッピングモール」と銘打っています。
ラストワンマイルの配達時間争いが加速に限界も?

ここ数年の間に、注文後に商品を15分前後で配達する「即時配送サービス」が新たに登場しました。海外で、ドイツ発のGorillasやJOKRなどがしのぎを削っています。国内では、2021年8月に東京・目黒でOniGOが「10分以内」をうたった即時配送サービスを始めました。
米国の事例をみると、即時配送サービスは、既存サービスの配達時間を短縮するという特徴のほか、2つの注目すべき点が存在します。
第一に、UberやDoorDashなどと異なり、配達人員を社員として雇用しています。あらかじめ社員が待機し、配達する準備をしておくことで、サービスの質を担保します。デリバリーを担う人手が不足する中で、福利厚生を充実させることで人員確保につなげるという側面もあるようです。
第二に、商圏に応じて、配達人員の商品の受け渡しに特化した「ダークストア」を最適な場所に配置することで、スピーディな配達が可能となっています。各店舗は、地域ごとの需要に応じた品揃えで、半径1マイル程度の配達先に10分前後で商品を届けます。一般の買い物客が入れない店舗なので、配達用に陳列を効率化できるのが利点です。
ただし直近の動向では、物価高騰に伴い経済状況が厳しさを増す中、各社は苦しい状況に置かれているようです。2022年3月には、Fridge No MoreとBuykというスタートアップ2社が倒産。そのほかのデリバリー事業者も事業縮小を余儀なくされています。これらの要因については、需要低下だけでなく、収益モデルが持続的でないとの指摘もなされています。
新興のデリバリー事業者に対抗する既存事業者
新興のデリバリー事業者に対して、実店舗を持つ大規模な米国の小売業では、EC商品の受け渡しについて通常の宅配に加えて、注文した商品を消費者が店舗で受け取るBuy Online Pickup In Store(BOPIS)が普及しています。例えば、米Whole Foods Marketや米Krogerは、一般客の商品の受け渡しに特化したダークストアとして実店舗を活用する形式をとっています。
効率重視の物流拠点に位置付けるダークストアと、衝動買いなどでの買い物機会を提供する小売店として特徴を併せ持つハイブリッドストアを構築する動きもみられます。
Amazonは、2020年8月、日用食料品を販売する店舗Amazon Fresh Grocery Storeの展開を始めました。配送センターであると同時に一般客も買い物ができる、いわゆる「ハイブリッドストア」です。専用スマートカート「AmazonDash Cart」を使えば、レジでの会計が不要で、いつでも買い物の総額を確認できます。店舗にとっては、常に正確な在庫数を把握できるという利点があります。
ドローンなどのテクノロジを活用した実証実験進む

コロナ禍では、ラストマイルに関連するテック企業も台頭しています。
例えば、自動運転車やドローンによる配送について、小売業と提携し、実証実験を重ねています。自動配送に特化した米Nuroは、米Krogerや米CVS Pharmacyと無人走行車による配送を検証。実用化に向けて検証を重ねた取り組みの結果、2020年12月にカリフォルニア州での初の公道走行の許可取得を発表しました。ラストマイルデリバリーの問題の一つである、ドライバー不足を解消する取り組みとして注目が高まっています。
国内では、エアロネクストとセイノーホールディングス、BOLDLY、セネックの4社が、茨城県の境町と連携協定を結び、実証実験に着手しました。目標は、2023年度中のレベル4のドローン配送サービス提供。レベル4では、有人地帯で補助者なしで目視外飛行できます。ドローンや自動運転バス、トラックなどの既存のモビリティを組み合わせた物流の最適化を目指しています。
具体的には、人が密集している住宅街のようなドローンが飛行できない地域には自動運転バスやトラックを活用して配送。一方農村部では、トラックとドローンを組み合わせた配送モデルにすることで、人手不足の解消だけでなく配送コストの削減にもつながると試算しています。
まとめ
今回見てきたようにラストワンマイル関連のサービスは、短いサイクルで新たなトレンドに沿ったサービスが生まれては淘汰が起きています。国内外で、企業同士のさらなる合従連衡が起きるかもしれません。重要なポイントは社会インフラとしての定着度合いでしょう。自動配送テクノロジーについては、コストや効率の問題から徐々に下火になっているとの指摘もあります。実装が進むのか、あるいは幻滅期を迎えることになるのか、今後の動向に注目です。