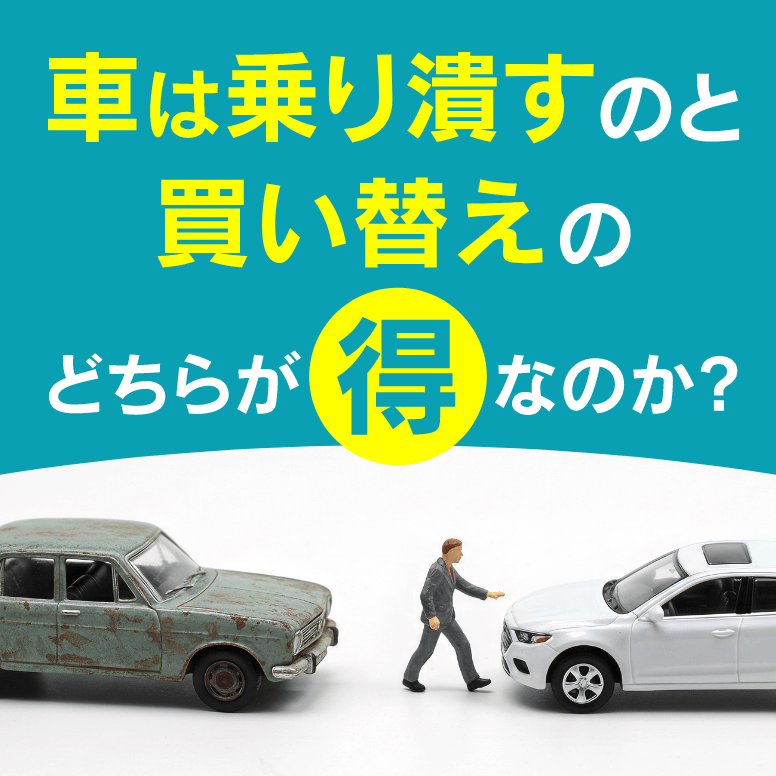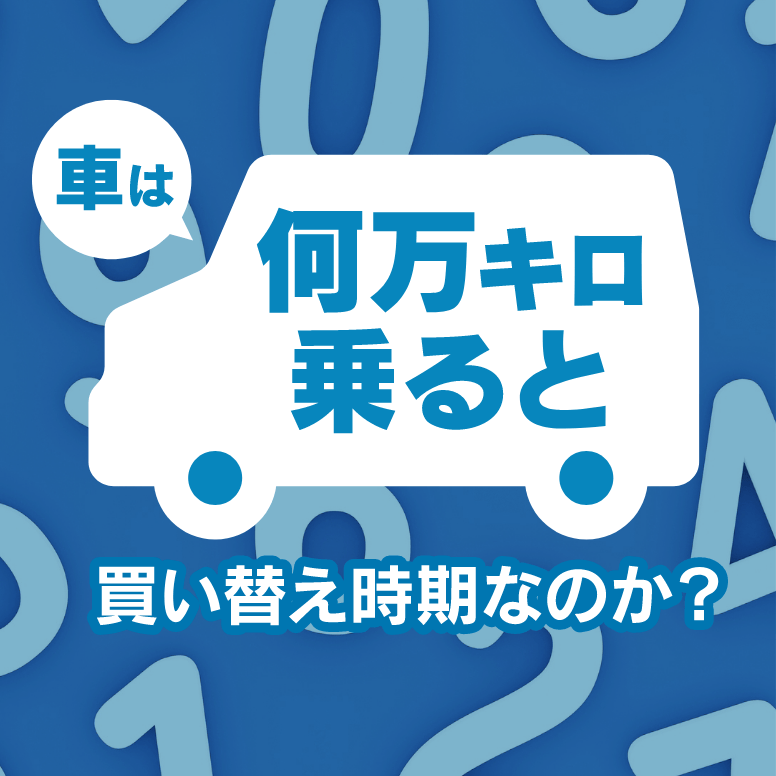新車の買い換えサイクルは人それぞれではありますが、「お得になる乗り換えタイミング」というものも存在します。この記事ではリセールバリューや車検費用、故障リスクといった視点から、車のお得な乗り換えサイクルについて詳しく解説します。
cars AI査定は、自動車業界のビッグデータをもとに独自のアルゴリズムでマイカー相場を瞬時に算出。個人情報不要で査定は最短30秒で完了。従来の買取業者からのしつこい電話やメールに悩まされることもありません。
また、AI査定結果は保存可能。cars会員になると査定履歴をグラフ化して推移を記録できます。日々変動するデータを常に自動更新するので毎日対象車両の価格チェックが楽しむことも可能です。
さぁ、あなたも今すぐAI査定してみよう!
cars MARKET スマート乗り換えで
ギフト券プレゼント!
車は何年で乗り換えるのが得?
乗用車の場合、乗り換えは3年、5年、7年、9年といった奇数年が一般的です。これは自家用乗用車の車検のタイミングであり、乗り換えは基本的に車検の有効期間が無駄にならない次回車検の直前、というのが前提になります。
カーリースにおいても5年、7年、9年という契約期間が多いのは、この車検のタイミングに基づくためです。
3年で乗り換えるメリット
3年での乗り換えは、車検費用をかけずに高年式のうちに車を手放すことができ、リセール面でも大きな優位性があります。以下で詳しく見ていきましょう。
A.現車を高く手放せる
新車登録から3年程度の初回車検実施前の車両は、高いリセールバリューが期待できます。一般的には走行距離もそれほどかさんでいないため、「高年式・低走行」であるケースが多く、中古車市場で高く評価されるためです。
特に走行距離が少ない車に関しては、かなりの高値が期待できるケースも少なくありません。人気モデルや需要のあるグレードなら、購入価格に近い金額での売却が期待できることもあります。特に残価設定型ローンを利用している場合、想定残価を上回る査定額が出れば次の車への乗り換えコストを大きく抑えることも可能です。
B.車検費用がかからない
自家用乗用車の場合、初回車検は新規車両登録から3年目に実施されます。そのため車検前に車を手放せば、車検費用の負担がありません。車検には通常、数万円~十数万円のコストがかかるため、これを節約できるのは大きなメリットといえるでしょう。
C.状態の良い車に乗り続けられる(新車に乗り換える場合)
通常の車の使い方であれば、3年程度であれば足回りやパワーユニットといった機関部分に不具合が出ることはほとんどありません。内外装のダメージもごくわずかでしょう。車の劣化が気になる前に乗り換えられるのは、3年乗り換えならではのメリットです。
また、先進安全装備やコネクト機能などは新しい車ほど充実しています。常に最新装備を搭載した車の乗り続けられるのもうれしいポイントでしょう。
D.任意保険の「新車割引」を継続できる(新車に乗り換える場合)
保険会社によっては、新車登録から一定年数(例:初度登録から25ヶ月以内など)に該当する車両に対し「新車割引」が適用されるケースがあります。3年ごとに新車を購入すれば、この割引を常に受けることができ、任意保険料の負担を軽減する効果も期待できるでしょう。
年間数千円~数万円の差になる場合もあるため、トータルで見ると決して無視できない点といえます。
5年で乗り換えるメリット
5年での乗り換えは車検1回分の維持コストで済ませつつ、特別保証の範囲内で使用でき、安心感と経済性を両立できる乗り換えタイミングといえます。
A.現車を比較的高値で手放せる
車は年式が古くなるほど車両価値が落ちていきますが、5年経過程度であればある程度のリセールバリューが期待できます。それなりの査定額を期待するのであれば、5年程度までが目安になるでしょう。
特に、メンテナンス記録がきちんと残されている個体や、外装・内装の状態が良い車両は、買取業者からも高い評価を得られやすくなります。
B.「5年で車検1回」のサイクルで乗り続けられる(新車に乗り換える場合)
5年での乗り換えの場合、継続車検を1回実施する必要があります。自家用乗用車の車検は初回登録から3年後、それ以降は2年ごとになるため、長く乗り続けると車検の頻度が上がり面倒に感じることもあるかもしれません。
その点5年での乗り換えであれば、「5年に1回」の頻度での車検で済むため、長期間同じ車に乗り続ける場合と比べ、車検の手間を抑えられます。
C.特別保証を継続できる(新車に乗り換える場合)
多くの国産車では、新車から5年間または走行距離10万kmまでの「特別保証」が用意されています。これはエンジンや駆動系といった重要部品が対象となっており、この保証期間中に乗り換えることで、予期せぬトラブルに見舞われるリスクを最小限に抑えられるでしょう。
さらに、新しい車に乗り換えれば、再びこの保証が初期化されるため、安心してカーライフを継続できるのもメリットです。
D.状態の良い車に乗り続けられる(新車に乗り換える場合)
車の技術進化は早く、5年も経てば運転支援システムやインフォテインメント機能に大きな違いが出てくるようになるでしょう。また、新型登場から5年以内には多くの車がマイナーチェンジをしており、サイクルの早い車種ではフルモデルチェンジするケースも見られます。
また、5年が経過するとタイヤやバッテリーなどの交換も必要になり、車の使い方によっては足回りのへたりや内装の傷みなど気になる点が出てくることも。
その点5年サイクルなら、装備が古くなり過ぎる前に乗り換えられます。
7年で乗り換えるメリット
車の平均的な保有期間にあたる7年での乗り換えは不具合を経験しにくい、フルモデルチェンジに合わせやすいなどのメリットがあります。
A.平均的期間で車を手放せる
一般社団法人 日本自動車工業会の「2023年度 乗用車市場動向調査報告書」によると、新車の平均保有期間は7.7年程度とされています。
多くの人が7年程度で車の乗り換えを実施しているため、中古車市場でもある程度個体数があり査定額はこなれてきている傾向があります。ただしきちんと管理されており、極端に長い走行距離でない限りはそれなりの価格で手放せることが多く、無理のないバランスが取れた乗り換えタイミングといえます。
B.大きな不具合なく車に乗り続けやすい(新車に乗り換える場合)
車両の使用年数が7年を超えると、部品の劣化や消耗によるトラブルが増え始める傾向があります。特にバッテリーや足回りの部品、電装系統などは経年劣化が進みやすく、故障の予兆が見え始めるタイミングでもあるのです。
7年での乗り換えは、そうしたトラブルが顕在化する前に次の車へ移行できます。
C.フルモデルチェンジのサイクルに合わせやすい
国産車の多くは、約6~8年のサイクルでフルモデルチェンジを迎えます。7年での乗り換えは、フルモデルチェンジのサイクルに合わせやすく、新型への乗り換えがスムーズにできるのもひとつのメリットといえるでしょう。
9年で乗り換えるメリット
中古車市場における車両価値の判断基準のひとつである10年を目前に控えた9年目での乗り換えは、査定価値が大きく落ちる前に車を手放し、予期せぬトラブルが本格化する前に次の車へ乗り換えるチャンスといえます。
A.価値が下がり切る前に車を手放せる
車は年式が新しいほど高値が付くのは先述のとおりですが、その中でもひとつの区切りとなるのは10年です。新車登録から10年を過ぎると市場では「10年落ち」として明確に区切られ、査定額がさらに大きく下がる傾向があります。
10年落ちになる前の9年で乗り換えれば、極端にリセールバリューが下がる前であるためそれほど高額ではなくてもある程度の査定額が付き、次の車への資金に回せるでしょう。
B.大きな不具合を経験しづらい
近年は車の性能が上がり寿命も長くなりつつあるといわれていますが、それでも登録から10年経過がひとつの目安といえ、10年目を目前に控えると、経年劣化による部品トラブルのリスクが高まります。
エアコン、サスペンション、電子制御系などの修理費がかさみ始めることも多く、突然の出費に悩まされるケースも。
9年目での乗り換えは、大きな不具合が起きる前、またはメンテナンス費用がかさむ状態になる前に乗り換えられるタイミングです。壊れるまで乗り潰すのではなく、ある程度長く使いたいけれど致命的な故障が起こる前には乗り換えたい、というときに適した選択肢といえるでしょう。
車の平均保有期間(乗り換えスパン)は?
実際のところ、世の中の多くの人がどのくらいの期間で車を乗り換えているのでしょうか。
一般社団法人 日本自動車工業会による「2023年度 乗用車市場動向調査報告書」によると、乗用車の平均保有年数(新車・中古車)は約7年とされています。これは、多くの保有者がこの年数をひとつの節目と考えていることがうかがえる結果です。
なお、同調査での保有年数の分布は以下のようになっています。
| 保有年数 | 割合 |
|---|---|
| 〜1年 | 約1% |
| 〜3年 | 約9% |
| 〜5年 | 約19% |
| 〜7年 | 約19% |
| 〜10年 | 約28% |
| 10年超 | 約24% |
車の乗り換えをおすすめするタイミング
車の乗り換えを検討すべきタイミングは、単に年数や走行距離だけで決まるわけではありません。生活環境の変化や車両の状態など、さまざまな視点から多角的に判断する必要があります。
ここでは、車の乗り換えタイミングの判断基準になるポイントを見ていきましょう。
現車に不便を感じ始めた時
ライフスタイルが変化すると、それまでは不満のなかった車が使いにくく不便に感じるようになることも少なくありません。
結婚や出産によって家族構成が変わった、趣味や仕事で荷物を運ぶ機会が増えた、高齢の親を乗せる機会が多くなったなど、生活の変化に伴って求める車の条件も変わります。また、運転頻度が増えれば燃費や乗り心地への意識も高まり、狭い車内や収納不足といった不満が表面化することもあるかもしれません。
自分の現在の生活に車が合っていないと感じたときは、乗り換えを検討すべきタイミングといえるでしょう。
10年10万キロを迎える前
日本の中古車市場では「10年落ち」「走行距離10万キロ超」というラインがひとつの評価の目安とされており、これを超えると査定額が大幅に下がる傾向があります。
いくら手入れをしていても、10年10万キロを超えた車は数字上の印象が先行してしまうため、リセールバリューを意識するならこのラインの手前で売却するのが賢明です。
フルモデルチェンジの前
車がフルモデルチェンジすると、乗り換え需要によって先代モデルが一時的に多く市場に出回るため、評価が一段階下がります。とくに人気車種ほど個体数が多くなるため影響が顕著になり、型落ちとなった瞬間に査定額が10万円単位で下がるケースも少なくありません。
そのため日頃からモデルチェンジ情報をこまめにチェックし、新型が発表されそうな気配があるとその前に動くことをおすすめします。
修理に高額な費用がかかる時
車のパーツは使用していくうちに摩耗するのはもちろん、あまり使用頻度が高くない場合でも経年劣化します。
特にエンジン回りやパワースライドドアのモーター、あるいはハイブリッドバッテリー、モーターといった高額部品が故障した場合、修理費用は数万~十数万円、場合によっては数十万円規模になることもあります。
年式や走行距離によっては、こうした費用をかけてまでその車に乗り続ける価値があるのか、判断に迷うケースも出てくるでしょう。しかも古くなった車は修理を終えた後に別の部位に不具合が出ることも多く、「費用をかけても不安が残る」という心理的ストレスがかかることも否定できません。
一定の年数・距離を超えた車で高額な修理が必要になったときは、将来の安心感や維持コストを総合的に考え、乗り換えも視野に入れてみるといいでしょう。
「欲しい!」と思える車が見つかった時
車の乗り換えに際して、経済性やタイミングだけでは語れない部分もあります。「この車に乗ってみたい」「所有したい」と思えるほど魅力を感じたモデルに出会ったときは、気持ちを優先した判断をしてもいいかもしれません。
車は日常の移動手段であると同時に、所有する喜びや満足感、そして時には人生の節目を彩る存在でもあります。本当に欲しい車を手に入れると理屈では測れない幸福感を得られ、カーライフの満足度も上がります。
心を動かされる車に出会ったときは、車検のタイミングなどにこだわらず乗り換えるのもひとつの選択肢です。
車の乗り換え時に考えるべきこと
車を買い替える際に考えるのは、タイミングだけではありません。今乗っている車のリセールバリューや乗り換え先の車についてもよく考える必要があります。
乗り換えで不便が生じないか
車はそれぞれサイズ感や搭載している装備に差があります。同じ車種の後継モデルに乗り換えたとしてもコンセプトが変わり、デザインや使い勝手が大きく変わっていることも少なくありません。そのため、新しい車については取り回しのしやすさや室内空間の広さ、荷室の容量などをはじめ、欲しい快適装備が搭載されているか、運転支援機能はどの程度充実しているかなど細かい部分までよく確認しましょう。
ミニバンからSUVへ、またコンパクトカーから軽自動車へなど、タイプや区分が異なる車に乗り換える場合は特に注意する必要があります。自身のライフスタイルや求める用途に適した車に乗り換えないと、不便を感じまたすぐに乗り換える必要に迫られることになりかねません。
リセールでどのくらいの乗り換え資金を確保できるか
新しい車を購入する際、多くの方が重視するのが「リセールバリュー」、つまり数年後にどれくらいの価格で手放せるかという点です。乗り換え時の出費は車両本体価格や諸費用だけでなく、下取り価格や買取価格によっても大きく変わります。リセールが高ければ次の乗り換え費用を軽減でき、ローン残債のリスクも抑えられます。
車種の人気度やカラー、グレード、走行距離、修復歴、整備履歴などの車の状態のほか、その時の市場のトレンドもリセールに影響するため、ある程度は運任せの部分もあります。ただし世代を超えて人気のある定番モデルや日本における定番色のホワイト系・シルバー系、ブラック系カラー、バランスが取れた中間グレードは査定で有利になる傾向があるため、その点を視野に入れた車選びをするのもひとつの方法です。
車を乗り潰すのは非合理なのか?
車を乗り換えることなく壊れるまで乗り続ける、いわゆる「乗り潰し」という選択肢もあります。車をある程度の年数で乗り換えるのか、乗り潰すのか悩むこともあるかもしれません。
ここでは、車を乗り換えずに乗り潰すメリットとデメリットを、それぞれ整理して解説します。
乗り潰すメリット
車を乗り潰すメリットとして挙げられるのは、車両の購入費用がかからないことでしょう。現在は車の高額化が進み、軽自動車でも100万円以下で手に入るモデルはほとんどありません。さらに車の購入時には、車両登録のための諸費用もかかります。
例を得ると5年で乗り換えるサイクルの場合、10年間で考えると2回車を購入することになります。いずれも諸費用込みの総支払額を250万円とした場合、5年乗り換えの場合は10年間で500万円かかりますが、乗り潰す場合は250万円で済みます。
車にはさまざまな維持費がかかるためどちらに合理性があるとは一概には言えませんが、「車両の購入費用」という点のみを比較すると乗り潰すほうが安く抑えられるのは明らかでしょう。
不具合がなければ車にかかるお金を最も抑えられる
車は年式が古くなるほどトラブルが多くなる傾向はあるものの、今の車は性能が良く、定期的な点検やメンテナンスを怠らなければ大きな不具合を起こすことなく寿命まで乗り続けられることも少なくありません。
カーライフを通して丁寧に扱えば、乗り潰すのはトータルコストを最も抑えて車に乗れる選択肢といえるでしょう。
乗り潰すデメリット
乗り潰しはコスト面でのメリットがありますが、年数が経過するにつれていくつか避けられないデメリットが出てきます。ここでは、乗り潰す際に注意すべき代表的なポイントを見ていきましょう。
税金が高くなる
毎年納税義務がある自動車税種別割は、グリーン化特例により新車登録から13年を経過すると重課され、税額が上がります。普通車で約15%、軽自動車で約20%の重課になるため、特に排気量が大きい車は負担に思うこともあるかもしれません。
また、年式が古くなると税額が上がるのは自動車税種別割だけではありません。車検時に支払う自動車重量税も、新車登録から13年経過で税額が上がることに加え、18年経過になるとさらに重課されるため注意が必要です。
そのため、長く同じ車に乗る方でも13年や18年といった税金が上がるタイミングで乗り換えを検討するケースも多くあります。
不具合発生リスクが高まる
古くなった車は、摩耗や経年劣化が気になるようになります。メンテナンスをしていても、部品の疲労やゴム系素材の劣化は時間とともに進行するため、新しい車と比較すると不具合のリスクが高まるのは避けられません。
特に10年以上乗り続けた車の場合、エンジンや駆動系などに不具合が出るケースもあり、その場合の修理費用はかなり高額になります。走行中に突然故障し、事故のリスクにさらされることも皆無ではありません。
故障時に部品が見つからない可能性がある
車のパーツの保管期限はメーカーによって異なりますが、生産終了から10~15年程度が一般的です。そのためこれ以上長く乗り続けている場合、車が不具合を起こしてもパーツが手に入らず修理できない、という可能性が否定できません。
汎用品や中古パーツで修理できるケースもありますが、かならずしも適合するパーツが手に入るとは限りません。この点は乗り潰すデメリットといえるでしょう。
まとめ
車の乗り換えにおいて、「どのタイミングで乗り換えるのが得か?」という問いに対する正解はひとつではありません。一般的には車検前がお得になるタイミングではあるものの、ライフステージの変化やフルモデルチェンジなどによってそのタイミングを待たずに乗り換える必要が出てくるケースもあります。
車の購入費用という大きな負担をできるだけ避けたい方には乗り潰すという選択肢もありますが、税金が高額になる、故障のリスクが上がるという点を考えれば、適切なタイミングで乗り換えたほうが快適なカーライフを送れるかもしれません。
今は、必ずしも車を購入する必要はなく、大きな出費なしに好きな車に乗れるカーリースなどさまざまな車の利用方法があります。そのため、手元の資金に縛られない車選びができるほか、資金繰りに悩んで乗り換えタイミングを逃すこともありません。
日々の使い勝手や安心感、そしてこれからの生活に合った移動手段として車とどう付き合っていくかを見つめ直し、適切なタイミングで最適な車に乗り換えることが満足度の高いカーライフを維持するために大切といえるのではないでしょうか。
cars AI査定は、自動車業界のビッグデータをもとに独自のアルゴリズムでマイカー相場を瞬時に算出。個人情報不要で査定は最短30秒で完了。従来の買取業者からのしつこい電話やメールに悩まされることもありません。
また、AI査定結果は保存可能。cars会員になると査定履歴をグラフ化して推移を記録できます。日々変動するデータを常に自動更新するので毎日対象車両の価格チェックが楽しむことも可能です。
さぁ、あなたも今すぐAI査定してみよう!
cars MARKET スマート乗り換えで
ギフト券プレゼント!